「大人たるもの見知った場所の”美味しいお店”を2つや3つぐらいは知っているべきである」
という価値観が、気づけば世の中を支配していたような気がする。
物心ついた頃から近所では幾多もの飲食店ができては潰れ、また新しい店ができたり、人々の間に食べログやぐるなびなどのサービスが広く根付き、テレビでは優れた飲食店を紹介するお笑い芸人がもてはやされたりしていた。
友達と遊ぶ時などにもよく気を遣った。
チェーン店は基本的になし。値段は安すぎず高すぎず。マニア向けすぎてもいけないが、ぐるなびなどで簡単に出てくるような場所ではないこと。こういった店選びに私は毎回苦心した。
東京の三軒茶屋周辺で育ち、銀座にある会社に勤めていたため、その時々に付き合いのあった友達は私に「美味しいお店を知っているはず」という期待を持っている子が多かった。
しかし、私は外食にほとんど興味がない。全くと言ってもいいかもしれない。
外食と言うよりも、食自体にそこまで興味がない。
健康に悪くなく、味や食感のクセが強すぎず、値段が高すぎなければなんでもいい、と半ば本気で思っている。
なので冒頭の「大人たるもの見知った場所の”美味しいお店”を2つや3つぐらいは知っているべき」という価値観に馴染むことができず、苦手だった。
世の中では「美味しい店」をよく知っている食通の人が、人間的に優れた価値の高い人物として称賛される傾向があり、理解につまずいた私はそういった価値観がますます苦手になり、距離を置くようになった。
”味覚に優れた人=人間的に優れた人”となるのは何故なのか?
この問いに対する答えを考えると、おそらく「味覚に優れる」ことは「良いセンスを持っている」=「優れた個体である」ことに繋がると連想されるからなのかなと思う。
それならば一応の納得はできる。
人間は基本的に優れた個体でありたいものだし、それを他の個体に顕示したいものだ。その感覚は私にも覚えがある。
ここから先が違和感の正体なのだが、人間には五感がある。(第六感まである人もいる。)
味覚はそのうちの一つに過ぎない。
他に四つの感覚があり、全てを合わせて人間は成り立っている。
視覚が優勢な人、聴覚が優勢な人、人の数だけそれぞれに強みがある。
どうして味覚だけが突出して重要視されるようになったのか?
少し話は変わるが、味覚に篤い信仰心を抱く人々の中には、無邪気に「世界の国々にはその土地ごとにそれぞれ美味しい料理がある」と信じている人たちもいる。
しかし、それは違う。
もちろん地域的に美味しい料理を常食している場所もある。
アジア圏や地中海圏、南米の一部地域やアフリカの一部地域など、パッと思い浮かぶだけでもたくさんある。
だが、それ以外の地域はどうかというと、「ここの住民はいつの代からか味覚を持たずに生まれてきているとしか思えない」というような粗食が常食のところもたくさんある。
日本にある◯◯料理レストランでご飯を食べたら美味しかったので現地に行って食べたら、さほどでもなかったという話はよくある。
それにははっきりとした理由があって、◯◯料理レストランのご飯が美味しかったのは、”日本にある”◯◯料理レストランで食べたからなのだ。
日本で商売を続けることができているということは、食通もどきの多い日本人の好みにある位程度合わせられているということだ。
本場の現地の人たちは、日々の料理が特別に美味しかろうがそうでなかろうが特に気にすることなく、ただその時手に入りやすいものを食べて生活をしている。
一汁三菜のような考え方はなく、マヨネーズをかけたパスタの上に味付けなしで焼いた鶏肉を乗せ、それを食べて終わり、といったレベルで平均だ。
日本で同じような食生活をしてそれを他人に知られると、おそらく眉を顰められる可能性が高い。
生活の中において、口にする料理が美味しいかどうかという項目が占める割合が高くないのだ。
逆に言うと、日本人は生活の中において、口にする料理が美味しいかどうかをかなり重要視している人が多いような気がする。
ここで話を戻したい。
人間に備わった5つの感覚の中で、味覚だけが突出して重要視されるようになった理由についての推測だ。
日本人はとにかく労働に従事している時間が長い。
私も東京で会社員をしていた頃があり、1日8時間働いて毎日きっちり定時で退勤していたが、それでも家に帰るとヘトヘトで何もできず寝てしまう日が多かった。
日本のサラリーマンのおそらくほとんどは残業をしているため、私などよりも更に疲れているはずだ。
そんな中でも優れた個体でいることは諦めたくない、そこまで強い目的はなくとも日常の中で少ないリソースを割かずに得られる娯楽が欲しい、そういう人々にグルメブームがうまくハマったのではないかと推測する。
評判を少し調べて店に出向き、お金を払えば誰でも美味しい料理を食べることができる。
美味しい料理を食べるのは楽しいし、いま世の中では美味しい料理をたくさん知っている人がセンスがいい人としてもてはやされている。
こうなったら、ある程度まとまった数の人間がそちらへ流れるのは簡単だと思われる。
私も海外移住のための貯金という目標さえなければ、グルメブームを楽しんでいたかもしれない。食に興味はないが、美味しい料理を食べるのは私だって好きだ。
それなのにこんな記事を1人で書くほどグルメブームに対して批判的なのには理由がある。
これからのことだ。
最初に書いておくと、私はヴィーガンやベジタリアンではない。
動物の肉は美味しいし栄養もあるし、食肉用に飼育される動物が特別にかわいそうだとか、そういうことも思わない。
人間の食事のために生まれさせられ、育てられ、殺される牛や豚がかわいそうだと言うのなら、同じく栽培され、摘み取られる野菜や大豆だってかわいそうなはずだ。
眼球や声帯などが人間の目に分かりやすい形で備わっていなくとも、この世に生まれ、栄えの時があり、朽ちて死んでいくという工程がある限り、それらは全て等しく”命”であるはずだ。
とはいえ、日々生活をしている中で、そんなに大量には肉を食べる必要はないなと思う。
1週間を振り返ると今週は肉を食べなかったな、という週もよくある。
かなりの面倒くさがりで忘れっぽい性格のためスーパーで買ってきた肉を期限内に食べ切るのが難しく、手を出しにくいという理由もあるのだが、そういう時も特に我慢しているという自覚はない。卵や豆乳などで栄養は十分に足りる。
あまり詳しくないし、なるつもりもないのだが、食肉の生産は環境に負担がかかるらしく、また食糧廃棄などの問題もある。
そういった犠牲の上で成り立っていたのが、ここ何十年かぐらいのグルメブームなのではないだろうか。
何か普遍的で崇高な目的があるならともかく、人間のふわふわとした一過性の娯楽のために犠牲を出し続けていていいのだろうか?
犠牲を出さないで生活を楽しむ方法があるはずだ。
グルメブームと、味覚に優れた人々を否定するわけではない。
むしろそういう人達はこれから、美味しいべジミートや植物性ミルクなどに対して感覚を尖らせて発展させていってほしいし、その感覚のベースになるものは、これまでのグルメブームの中で磨かれた確かな味覚である。
特に味覚に優れたわけではないが、なんとなくグルメブームに乗っかっていた人達もいるかと思う。
変化が必要なのはそういう人たちだ。
美味しい料理を探究し続けることが果たして本当に自分が好きなことなのか? 得意なことなのか?そうではなかった場合はある程度食生活を見直した方がいいかもしれない。
それがどうしても必要だというわけではないなら手放して、犠牲を減らす方へ流れる人が増えるといいなと私は思う。
感覚は人の数だけ違う。
その違いが価値を生み、さらに上の価値を目指してこれまで人間は切磋琢磨してきた。だがその裏には常に犠牲がつきものだった。
感覚の違いを生かして、犠牲をなるべく出さずに生活を楽しむ方法をみんなで探していく、これからはそういう時代になっていくといいと思った。

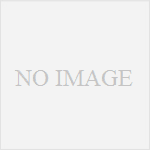
コメント